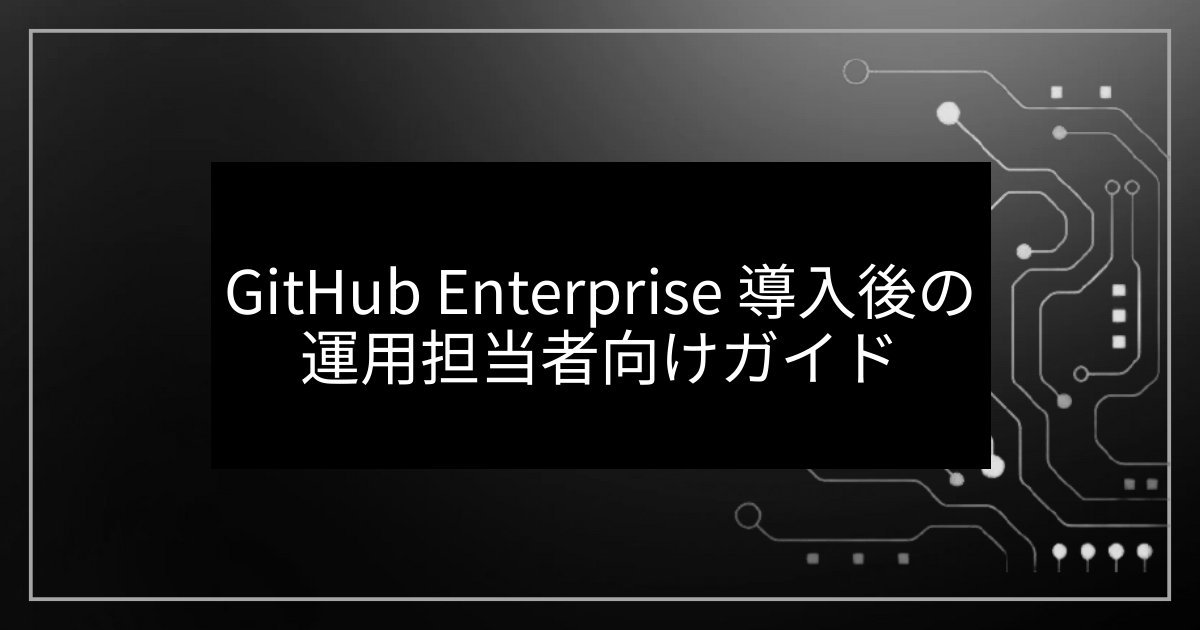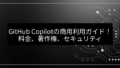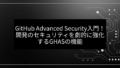GitHub Enterpriseを導入し、いざ運用フェーズに入ると、ユーザー管理やセキュリティ、開発プロセスの改善など、新たな課題に直面するものです。ここでは、日々の運用業務を効率化しながら、企業の知的財産を守るための実践的なヒントをご紹介します。
高度なID管理とアクセス制御で運用を自動化する
大規模な組織でのユーザー管理は、運用担当者にとって最も大きな負担の一つです。GitHub Enterpriseの機能を活用して、この作業を効率化・自動化しましょう。
- シングルサインオン(SSO)とSCIM連携
OktaやAzure AD、Google WorkspaceなどのIDプロバイダーと連携し、SAML認証によるシングルサインオン(SSO)を導入しましょう。これにより、ユーザーはIDプロバイダーの認証情報だけでGitHubにアクセスできるようになります。さらに、SCIM(System for Cross-domain Identity Management)を組み合わせることで、IDプロバイダー側でユーザーの追加や削除、チームへの割り当てを自動的にGitHubへ同期できます。手動でのアカウント管理が不要になり、運用負荷が劇的に軽減されます。 - チームの活用とリポジトリの可視性管理
プロジェクトやチームごとに「チーム」を作成し、チーム単位でリポジトリへのアクセス権限を付与しましょう。これにより、メンバー個人ごとに権限を設定する手間がなくなり、アクセス制御がシンプルになります。また、特定のチームのみにリポジトリを公開する設定にすることで、情報漏洩リスクを最小限に抑えられます。
GitHub Actionsで開発ワークフローを統一・自動化する
GitHub Enterpriseの真価は、統合されたCI/CDツールであるGitHub Actionsにあります。GitHub Actionsは、コードの変更をトリガーに、ビルド、テスト、デプロイなどの一連のタスクを自動実行できるプラットフォームです。この機能を活用することで、開発ワークフロー全体をGitHub内で完結させ、品質と効率を同時に向上させることができます。
- 再利用可能なワークフローを作成する
組織内で共通して利用するビルドやテスト、デプロイのプロセスを「再利用可能なワークフロー」として作成しましょう。これにより、各チームが独自のCI/CDパイプラインを構築する手間を省き、開発プロセスのばらつきを防ぐことができます。 - セルフホステッドランナーで環境を最適化する
社内の特定ツールが必要なビルドや、ネットワーク内部からしかアクセスできないリソースを使ったテストなど、特別な環境でのワークフロー実行が必要な場合は、「セルフホステッドランナー」を導入しましょう。これにより、GitHubのホスト環境に縛られず、柔軟なCI/CDパイプラインを構築できます。
GitHub Advanced Securityで継続的なセキュリティを実現する
企業の知的財産を守るには、開発プロセスにセキュリティを組み込むことが不可欠です。GitHub Advanced Securityは、GitHubに統合された包括的なセキュリティソリューションであり、開発ライフサイクル全体にわたって脆弱性や秘密情報の漏洩リスクを自動的に検出・防止します。この機能を最大限に活用して、自動的な脆弱性検出と監視体制を構築しましょう。
- GitHub Advanced Securityの全機能を利用する
- Code scanning 静的解析ツールとして、コード内の潜在的な脆弱性やバグを開発の初期段階で検出します。
- Secret scanning パスワードやAPIキーなどの機密情報が誤ってリポジトリにプッシュされるのを防ぎ、情報漏洩を未然に防止します。
- Dependabot 依存関係にあるライブラリの既知の脆弱性を自動的に検知し、バージョンアップを促すプルリクエストを自動で作成します。
- 監査ログAPIで監視体制を構築する
GitHub Enterpriseの監査ログは、ユーザーのあらゆる操作(リポジトリの作成、権限変更、ログイン試行など)を記録しています。このログはAPIを通じて取得できるため、外部のSIEM(Security Information and Event Management)ツールと連携することで、不審な挙動がないか継続的に監視することが可能です。
GitHub Enterprise Server(GHES)からCloud(GHEC)へのライセンス切り替えについて
すでにGitHub Enterprise Server(GHES)を導入済みで、クラウド版であるGitHub Enterprise Cloud(GHEC)への移行を検討している運用担当者も多いでしょう。オンプレミスからクラウドへの移行は、運用コストの削減や管理負担の軽減につながりますが、計画的な実行が不可欠です。
- 移行のメリットと計画
GitHub Enterprise Cloudへの移行は、インフラ管理の手間が不要になり、常に最新の機能が自動的に適用されるという大きなメリットがあります。さらに、ハードウェアやサーバーの運用・保守コスト、データセンターの維持費、およびそれらにかかる人件費が削減できます。移行計画を立てる際は、移行対象のリポジトリ数、ユーザー数、移行期間、ダウンタイム許容範囲などを事前に確認しましょう。 - 移行ツールの活用
GitHubが公式に提供しているGitHub Enterprise Importerなどの移行ツールを活用することで、リポジトリやユーザー、プルリクエスト、チームなどのデータを効率的に移行できます。手動での移行作業は大きな手間とリスクを伴うため、公式ツールを利用することを強く推奨します。 - 移行後の運用体制の再構築
GHECへの移行後は、GHESでの運用とは異なる部分が出てきます。IPアローリストの設定、監査ログのAPI連携、GitHub Actionsのランナー環境の見直しなど、新しい環境に合わせた運用体制を再構築することが重要です。
GitHub Enterprise Cloud(GHEC)からServer(GHES)へのライセンス切り替えについて
すでにGitHub Enterprise Cloud(GHEC)を導入済みで、より厳格なセキュリティ要件やオンプレミス環境での運用が必要となり、GitHub Enterprise Server(GHES)への移行を検討するケースもあるでしょう。このライセンスの切り替えは、GHESからGHECへの移行とは異なり、公式ツールが存在しないため、慎重な計画と手作業が必要です。
- ライセンスモデルの理解
GitHub Enterpriseのライセンスは、ユニークユーザー数に基づいています。エンタープライズプランを契約している場合、GHECとGHESの両方を利用する権利が含まれています。ただし、GHECからGHESに切り替える際は、GitHubの営業担当者を通じて、GHESの利用に必要なライセンスファイルを別途取得する必要があります。 - 移行の計画と準備
GHECからGHESへの移行は、リポジトリやユーザーデータ、プルリクエスト、Wiki、Issueなどのすべてのデータを手動で移行する必要があります。GitHubのAPIやサードパーティ製のツールを活用して、GHEC上にあるデータをエクスポートし、自社のGHES環境にインポートします。GHECからGHESへの移行は、多くの場合、GHECの利用料に加えて、GHESの運用にかかるインフラ費用や人件費が発生するため、トータルのコストは増加する可能性があります。 - 移行時の注意点
- ダウンタイム 移行作業中は、データの整合性を保つため、GHEC上のリポジトリへのアクセスを一時的に制限する必要があります。ダウンタイムを最小限に抑えるための計画が不可欠です。
- データの完全性 手動での移行は、データの一部が欠落するリスクがあります。移行完了後には、データの完全性を慎重に検証する必要があります。
GHECからGHESへの移行は、GHESからGHECへの移行と比べて複雑なプロセスを伴います。GitHubの営業担当者やプロフェッショナルサービスチームに相談する他に、GitHubの認定代理店に相談することも強く推奨します。GitHubの認定代理店は、多くの企業でのGitHub導入・移行プロジェクトを成功させてきた実績があり、技術的な知見やノウハウを持っています。移行計画の策定から、複雑なデータ移行、移行後の運用サポートまで、一貫した支援を受けることで、リスクを最小限に抑え、スムーズな移行を実現できます。
まとめ
GitHub Enterpriseは、単なるコード管理ツールではなく、企業の成長に合わせて柔軟に対応する強力なプラットフォームです。
運用担当者として、自社のセキュリティ要件や運用の負担を考慮し、ServerからCloudへ、あるいはCloudからServerへの移行を検討する機会があるかもしれません。その際は、GitHubが提供する移行ツールや、GitHub認定代理店の専門的なサポートを最大限に活用し、リスクを抑えながらスムーズな移行を実現してください。
GitHub Enterpriseの機能を使いこなし、変化するビジネス環境に合わせた最適なプラットフォームを選択することで、開発プロセス全体の効率と安全性を高め、企業の競争力向上に貢献できるでしょう。